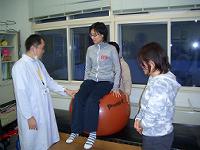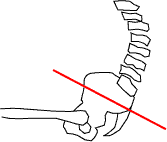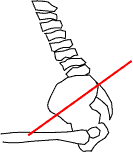東京大学先端科学研究センター中邑研究室の院生の平林さんが久々のアンケート調査に訪れていました(^-^)
平林さんの研究によると、筋ジストロフィー(デュシェンヌ型)の方では、人生の大きな谷が二つあると指摘しています。まずは歩けなくなった時と、そして手動車いすから電動車いすに変わったときだそうです。だんだんできなくなる不安の思いと自分によせる期待が葛藤となって現れているのではないかとのお話でした。そこで、手動車いすを導入しないで、簡易電動車いすの導入で、この2つめの谷(気持ちの落ち込み)を軽減できるのではないかと指摘されていました。実際、手動車いすを長く使用することで変形を助長しているとの報告もありますから、本人の気持ちを考慮しながら車いすの導入を単に「あるけなくなったから」と運動機能ばかりに焦点をあてないように注意が必要だと思います。
10月には、イタリアのAAATEで発表されるようです。
また、福祉情報工学研究会では、支援機器利用効果の長期的変動に関する評価尺度の開発-デュシェンヌ型筋ジストロフィー者のパソコン利用を対象として-で発表されています。