いよいよ。北海道にも冬到来です。
みんなの、冬ごもり生活のスタートです。
記事一覧
トップ
電子工作女子のすすめ
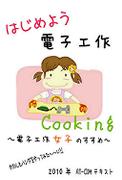
先日、コミュニケーション支援技術研究会の講習会でつかった資料です。
今回は、電子工作女子になるために、お料理になぞらえて電子工作の実践をしました~。
テキストはこちら。ご自由にどうぞ。
http://koresupe.sakura.ne.jp/koubeatcom.pdf
なににしばられてる?
実は、一度卒業式を迎えたへたけんは、密かに、10月中頃より、第2シーズンを開始されていました。
第2シーズンは、他者の理解。
人間作業モデルという、理論をつかって、自分たちがなぜ、不安になるのかを解き明かそうという時間になっています。
これまでは、自分の買ったお気に入りのものという、お題でそれぞれどのような理由でそれを選んだのか、質問力を養いました。
本日は、ちょっと、脱線して、「僕らは何に縛られているのか?」
話し合うことになりました。
・病気 ・空気感 ・寒さ
・人間関係 ・体調 ・決まり
・ストレス ・周囲 ・へたれ
・時間 ・みんな一緒感 ・孤独
・環境 ・病院 ・責任
・活動(仕事) ・患者(立場) ・政治
・発言
・みえないもの ・場面(部屋がせまい)
あらら。。。
これをみると、時間・空間・自分・他者と、あらゆるものから縛られている。
でも、縛られているというよりも、自らが縛られにいっているようなもの。
次回は、このような縛られ感からの脱却です。
IPADで自由自在
脊髄性筋萎縮症のSMAの子がIPADを使いこなしていますよ!
任天堂DSの一工夫
近々、新しい任天堂DSのゲーム機がでるようですが、こちらでは、もっか初期タイプのDSの改造におおわらわです!
とはいっても、改造は、各ボタンを1入力もしくは、複数のスイッチで押す対応のみ。
残念ながらタッチスクリーンの操作までの工夫はできていません。
それでも、ゲームで遊びたいという欲求は多いようですよ(^O^)
実ができました(^^)
iPad登場!
いよいよ、発売されたiPad!
新製品に目がない、彼らも早速手に入れた方がいましたよ(^_^)v
さて、そこで問題となるのが、使い勝手。
購入者の一人の『まこと』くんが、次のようなことをいっていました。
「画面が、おささる。。。」
お猿ではありません。。
どうやら、画面上のアプリボタンを押す際に、他のボタンもさわってしまうようです。デュシェンヌ型や、ベッカー型筋ジストロフィーの多くが、手をテーブルから浮かすことが難しくなるので、起こってくる問題です。

さて、それでも、テーブルの高さを低くすることで、解決できましたが、今度は、画面をみるために下を覗くような姿勢になってしまいます。
また、電源ボタンを押すときに。。
「はははっ。回ってしまう。。。」
力を横に向けていれてしまうと、iPadがまわってしまうようです。
さて、どんな工夫をしていけばよいのか?
ぼちぼちと、iPadを解剖していきたいと思います!(*^_^*)
学校祭準備ちゃくちゃくと!
車いすをスイッチでうごかす!
福祉機器クラブの発表でした!
本日は、福祉機器クラブのメンバーの発表の日。
残念ながら、『おぐ』は、お休みでしたが、『なべ&よっしー』が交互に発表と質問を行いました。
・なべ:ファイル 897-3.pdf
・よっしー:ファイル 897-2.pdf
なべちゃん、一人奮闘中
八雲病院で、人気の「スティックホッケー(フロアホッケー)」
ですが。。
その特徴はいかに?と、我らが『なべちゃん』が自らの身体をつかって実験です!
スティックホッケーは、卓球の球ぐらいの大きさのボールを相手ゴールに多く入れたほうが勝ちといういたって、ルールは簡単な競技。
しかし、ここに来て大きな課題があることに気がつきました。
「下が、みえない。。。」
そうです!
坐位保持が困難になってくると、背もたれに寄りかかった姿勢になりますが、そうすると、スティックの先が見えない。ボールを見えるように、スティックを長くしてしまうと、今度は、回転半径がおおきく、周囲のプレイヤーにぶつかってしまう。。
どうやら、このスティックホッケーというスポーツでは、ボールを操る際に、スティックの先端でボールの位置を確認するという視認性が求められるようです。
確かに、ボールがみえなくても、ある程度、ボールの位置を予測してスティックを合わせることもできますが、そのぶん、ミスも多くなるようです。
ボールが見えるように、身体をおおきく前に倒した位置で車椅子の姿勢を調整したいとの要望も聞かれますが、そこは、身体の変形予防との相談も。。
そこで、なべちゃんには、自分たちが移動できて、競技性もあり、かつ、足下を覗かなくても楽しめる、新スポーツを考案してもらうようにお願いしておきました~。
なんかごりごり。
今仙社の電動車椅子のミニジョイスティック。以前は、タカチのプラスチックケースを流用していましたが、現在は、型どりしたパッケージに収納されています。
しかし、本日一人の青年が。。
「なんか、ごりごりする~」との相談を抱え、OT室に。。
どうやら、ジョイスティックを傾けると、なぜかひっかかるとの話。
そこで、中をのぞいてみると。。。(注意!普通は覗かないように!)
ジョイスティックと外側のパッケージの部分に、ボールベアリングが4個ついており、滑りをよくしているようなのですが、このボールベアリングが、錆びていたよう。。
「汗っかきだからね~(笑)」
とりあえず、ボールを外して応急処置。
彼らの周りには、思わぬ、出来事がまっています。(*^_^*)
中邑先生の訪問です。
ひさびさの中邑先生の訪問です。
今回は、ニューメンバー『おぐちゃん』の面接をかねて、ニューツール『iPad』のお披露目でした~。
一同、へーーー。と、新しいツールにくぎつけ(^_-)
さて、今度は、この4月から福祉機器クラブのメンバーの学習を披露!
自分たち自身、障害を持っているからといって、いろんな見方できるとは限らない。
様々な視点で、ものを観察できる目利きが必要です。
その一つとして、身体を知ろうで取り入れた、人骨模型を使い、自分たちの座りを学習したことを紹介しました~。
へたれ自慢研究会 卒業式
毎週金曜日の午後のひととき。
みんなのへたれ自慢を聞いてきたサロンも、ついに1年つづきました。
1年をむかえて、それぞれのメンバーの個人発表が終わったところで、本日は、卒業式!
みなさん、どんな変化がありましたか?
自分が「へたれている」と感じたとき、きっと、それまでとは、違う自分の姿に気づくと思います。
では。また会う日まで。。
動きのしくみ
福祉機器研究会
福祉機器研究会のメンバーは、現在3名。
4月より個人個人、テーマをきめて、観察を中心に、「人の特性」「活動の特性」「環境(道具)の特性」を見いだす視点の勉強中です。
さて、本日は、フィールドワーク!
美術の授業におじゃまし、これまでの視点を活かしながら、どんな観察ができるかを試してきましたー。
「なぜ、左手に右手をのせて、絵を描いているのだろう?」
「姿勢は、これでいいのだろうか?」
ちょっとづつ、観察する視点が変わってきていますよ。(^-^)
ほねほねロック
みたなー~。(*_*)
ほねほねロックの歌を知っている人は、おそらく30代。。
さて、福祉機器研究会のメンバーは、人骨をつかって自分たちの身体の勉強をしているようですよ。(*^_^*)
車椅子にすわっていて、「おしりがいたい」といっても、いったい、どこが痛いのだろう?
身体のどこが変形してくるのだろう?
そんな疑問をさわって、観察しながら解決していますよ!
学校祭準備はじまる。
みなさん7月にある行事と言っこえばなんでしょう?
お祭り?夏休み??プール???
正解は。。。『学校祭です(^o^)/』
コレスペも毎年参加させてもらってるんですね~
今回は新メンバーの『いっち&いず』コンビが
準備を始めました。
内容はまだ秘密!お楽しみに~(^^)/
ほのぼの。
教育の情報化に関する手引
文部科学省で、小・中学校等の新学習指導要領に対応した「教育の情報化に関する手引」が公開されています。

































