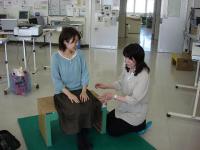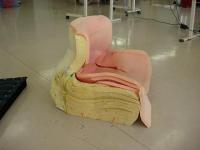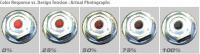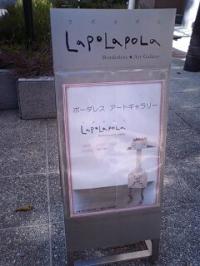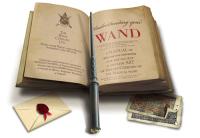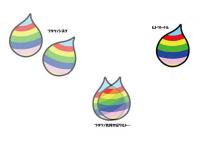以前(10年前)、いただいた文面を紹介したいと思います。
(脳性まひを持ち、就労されている方からの意見です。)
障害を持つ者と健常者との違いって、身体的にハンデを背負っているかどうかと言うのは誰が見ても当然の違いですが、そんなことは「単なる個性」と片付けてしまう障害を持つ者が多くなってきていますし、私自身もそんなことはどうでも良い細かい事だと思います。
一番の違いは、そこから派生した結果でしょうが「選択肢」の数の違いではないでしょうか?
就労に限らず、移動手段、就学、住居、資格取得、...etc どこを見ても障害を持つ者にはノーマルな状況で利用するには難しいものばかりです。
就労することに情熱を傾ける事は、その中でも大変エネルギーを必要とする事であり、叶わなかった時の挫折感も大きな事ですよね。
「仕事から帰ってくるのが遅くって」とか「今仕事が忙しいの」って言う言葉にはメールフレンドに限らず、ボランティアに来て知りあった人達、揚げ句には家族でさえ羨ましく思う事は否定できません。
でも、これって就労していないからそう思うのではなく、就労する事を選択できなかったから思う事だと私は思います。
先日もお話ししましたが、働きたい気持ちを持っている人に対して「無理して就労することを目的としなくても」とは決して思いません。
むしろ、そう思っている人に対しては積極的に応援したいと思っています。
たとえ寝たきりであっても、今の時代は何とかなるでしょう。
要は、障害を持った者自身が「何かしよう」と思い、行動を起こす事が肝心であり、「周りが何とかしてくれるまで待っていよう」と思うと、いつまで経っても何も起きないのではないでしょうか?
私としては、先生の近くで在宅にいる人たちの気持ちを理解するところまで至っていないので、彼らの心がときめくような誘い文句は言えませんが、具体的に彼らが知りたい事を聞いてきた時には、出し惜しみせず伝えていこうと思っています。
少なくとも、向上心有る仲間達がこれからも私達の職場を選択してくれるように努力していこうと思っています。
只、正直なところ就労しただけで鼻高になってしまう障害を持つ者(自分を含めて)って、多いですよね?
就労しただけで、全ての目標を達成してしまったかの様な錯覚に陥り、就労していない仲間を見る目が変わってしまうことって、障害を持つ者の世界では良く有ることだと思います。
私自身の心の中にも、そんな気持ちは無いとは言えません。
しかし就労することは、ハンデを背負っている者にとっては確かに高い目標であり、そこに向かっていく努力と達成したときの喜びは、その本人にとって(又は周りの人たち)は、とても大きな励みであり、健常者には考えられない程の成長と自立心を与えてくれるものだと思います。
でも、それ以上に思うことは「それだけで満足しないで、いろんなことにもっと貪欲に挑戦して!」これが私からの唯一の願いです。