吉田先生の講義であった、慣性モーメントを感じる実験をしてみました!
慣性モーメントが小さくなとどうなるのか?
続きはこちらで
ファイル 426-3.mpg
アイススケートのスピンにも、この原理が使われているんですねー。(*^_^*)
トップ
吉田先生の講義であった、慣性モーメントを感じる実験をしてみました!
慣性モーメントが小さくなとどうなるのか?
続きはこちらで
ファイル 426-3.mpg
アイススケートのスピンにも、この原理が使われているんですねー。(*^_^*)
卒業式当日。
いつにもまして、厳粛な雰囲気の中、迎えた卒業式。卒業生をおくりだす在校生も、ビシッと衣替えです!
式終了後、この春から新しく仲間になる期待の新人『みやぴー』くんが早速、挨拶に来てくれましたよ!
「4月からお世話になります。よろしくお願いします!」
緊張した面持ちのなか、温かくみんなから歓迎されてました。
もえあがれー、もえあがれー、エトダムー。
中邑研究室のお仕事を手伝うべく、福祉機器製品情報の更新作業をすすめる、メンバーら。
今日は、OT室で、なにやら、電話をかけたいと。。。
「もしもし、わたくし、東京大学先端科学研究室の『えと』ともうします。・・・略」
おーー。何かの台本を読み合わせをしているような、話。すでに電話をかけているとはしらずに、話かけてしまってごめーーん。
さて、一流の企業戦士になるべく、電話の応対には苦労しているようです。
君は、生き延びることができるか!
みえるよ、ららあ。
「今度は、ヘットセットを用意してあげるねー」
学んだこと、気づいたこと
・自分の「今」の状況を知ることが大事だということ一つのことだけではなく、いろいろ考えること!悩みは一人で抱えるのではなく誰かに相談すること。
・いろんな方向から見ないと、コミュニケーションが上手く取ることができないことを学んだ。1回目の講義でみんなが考えていることがわかった。
・いやなことなどの、共通している点があった。医療費が年間でどれくらいかかっているかわかった。
・普段このようなことを考える機会がないので、今回の3回の進路学習の機会は、生活を考えるいい機会になった。
・意外と自分と同じことをみんな経験して感じていた。そんな自分たちだからできることや伝えられることがあって、その中にあるとても大切な物を大事にして。自分のやりたいことして自分からいろいろな想いを伝えられるようになりたい。だからこそやっていかなければならないことや、解決するべき問題。どれも人の力を借りなければできないこと。だからどんなことにも協力して取り組むことが必要。そうすることで人との繋がり広げていきたい。そして一人ではできないことをいろんな人と築いていきたい。
・自分がいろんな所に支えられてることと、自分にどれだけのお金
がかかっているのかがわかった。
・色々なことに気づけて良かったです。
・もっと、自分の先(未来)のことを考える必要があると思った。
・自分の考えの甘さ、もっと考えたらよいことがわかりました。
感想
・とても勉強になった。まだ知らないことがあると思うので学習したいなと思った。
・自分たちが生活するために掛かっているお金の金額があまりにも高く驚いた。みんなの考えや体験談などが聞くことができとてもよかった。(共感できた)卒後への見通しがもててよかった。
・普段友達が考えていることがわかって、よかった。勉強になった。
・今までにない取り組みで楽しかった。今後も進路学習会を続けていったらよいと思う。
・その人によって気づけることがあるから、人によってそれぞれ出来ることが違う。一人一人の個性があって協力して支え合うことができると想った。今考えられる卒業後の自分は病院に居ると思う。それは医療のことよりも、家だとまずやりたいことは見つからないと思う。もしあったとしても身動きがとれない。病院ほど行動ができない。やりたいことを見つけるためには自分にできることを増やして病院でコレスペや友達と行動するうちに活動範囲を広げられると思った。だから病院しか想像がつかない。家に居たところで自分を広げられない。
・みんなの正直な意見が聞けて良かった。
・少し話しが難しかったけど、わかって良かった。今度機会があったらでいいので、やってほしいです。
・『おさむくん』らしさ出ていた授業で、とても楽しい雰囲気でした。
・すごく勉強になりました。また『おさむくん』の授業をうけたいです。
『おさむ』さんへのメッセージ
・もう少し、話す機会がほしい。普段話さないことをもっと話したいと思った。
そぐと、コレスペで活動するのでよろしくお願いします。また、僕たちのために学習会を開いてくださりありがとうございます。病棟が同じなのでわからないこともたくさん聞くと思いますので、よろしくお願いします。
・自分たちがかかっているお金がどれくらいかを教えてくれてありがとうございます。まだなにかあれば話をしにいきます。
・今回の進路学習会は、よい時間になったと思いました。今後も頑張ってください。
・大事なことを教えてくれてどうもありがとうございました。
・お互い色々頑張ろう!!授業ありがとうございました。
・これからも頑張ってください。僕もがんばります。
関西リハビリテーション病院リハビリテーションエンジニア、吉田直樹先生による講義が北海道文教大学人間科学部作業療法学科でありました。
吉田直樹先生は、田中OTの恩師!
久々にお顔を拝見し嬉しく思いました。
講義は、基礎の運動制御のお話。
慣性モーメントの力学的特性の理解から、フィードバック制御、フィードフォアード、ニューラルネットワークの制御入門のお話まで幅広く学べる時間でした。
スイッチ適合一つとっても、実に奥が深い!!
『でんじろう先生』ばりの実験を交えて行われたので理解しやすくおもしろい講義でした。(*^_^*)リハビリ病棟の下の仮想研究室
人が、石や紙で情報を伝える手段をもって、何千年になるのでしょうか?
今では、鉛筆の変わりにパソコンを使って情報を記録することができるようになったわけですが、このキーボードとマウスという入力手段よりも、よいものがなかなか生まれていません。
発想を根本から変えなければいけないのでしょう。
さて、今人気のiPhoneですが、こんな入力方法のようです。
iPhoneでのフリック入力
フリックというのは、『はじく』という意味。
これと、予測変換機能を合わせると、こんなに早くに文章が入力できるようです。
ペンも使えますので、障害を持つかたにも使えるかもしれません。
雇用の閉塞感。今、働き方が問われている。人間らしさとは?
この話題がよく取り出されますが、どんな状態なのでしょう?
お金とは?と問われ、多くのかたが、生きていくために必要なものと答えると思います。また、同じく、「はたらくとは」では、お金も大切だが、それだけじゃない。人の役に立つなどといった価値を示すかたもいるでしょう。
お金を得るということは、時間×労働です。昨今、人がモノとして扱われているとささやかれていますが、儲けるというシステムでは、常に人は商品価値として労働力(量)が評価されてきたのではないでしょうか?
障害者就労や、定年後の再就職も、可能な限り、この価値観への参加を促す仕組み作りのような感じがします。
障害を売りにするといった視点も、自分のあるものを利用するという商品価値にする試みなのです。
また、一方で、人は人のつながりを求めています。本来、人はつながりの中で生きていくことができました。このセーフティーネットが、切り離された状態。つまり、「モノ」と、「つながり」から、排除された結果が、貧困の状態を生み出します。
私達は、この「人のつながり」と「モノ」の価値のバランスの中で、現代の「はたらく」世界に生きているのかもしれません。
自分が立つ位置の環境によって、どちら側の世界の価値観として写るのか?
コレスペは、この両者の価値観を内包したコミュニティーだと感じています。
自転車操業で更新している、コレスペニュースですが、インターネットにアクセス出来る人だけでは、もったいない。(>_<)
ぜひ、日頃からお世話になっている、職員にも、僕らの活動をしってほしい!
そんな活動が始まります。
まずは、どんなテーマで紹介していこうかと話し合いを持ちました。
数回のこうしたミーティングを重ねて、彼らも一皮むけました!
普通、どこの会議をみても、話す人は、特定の人。沈黙が長く続くものですが、このときは違いました。
おもしろいことを競い合って共有するかのごとく、我先に、発言をしていました。
思うのですが、こうした雰囲気って、お互いに失敗しても許せる空気感でないと、できないですよね。
さて、どんな内容が紹介されていくのか今から楽しみです。
今春卒業を迎える『みやぴー』くんの歓迎会がコレスペで開かれましたー。(*^_^*)
面談形式で、迎えたメンバーは、3名。
さて、どのような話が交わされたのか。。聞き耳を。。
Q.「コレスペのイメージって?」
「仕事をやったり協力して活動している感じ。自分の可能性を伸ばすところかな・・・」
Q.「得意なことは?」
「イラスト!特に似顔絵かな。まだ練習が必要だけど、トレースもできます。」
「絵以外では。。。スティックづくりの「アイディア」を出したりするのが好きです。」
じゃあ。。苦手なことは?
「コミュニケーションが苦手。。です(~o~)。自分の思いを相手に伝えるのが苦手。(無理してしまう。焦ってしまう。。)」
→性格的なものは直せないけどね。。
→みんなで、チームでできることもあるよね。
じゃあ。「苦手」ではなく、作業的に現時点で「できない」ことは?
「自分のイメージや想像で絵を描くことが苦手です。」
やってみたいことはある?
「まずは似顔絵。人から注文をうけてみたい。」「後は、絵をいかして絵本を作りたい。想像して物語りをつくりたい。」「人の役に立ちたいです!」
こんな感じのやりとりが、繰り広げられた40分でした(*^_^*)
『みやぴー』からの質問も、みなさんの悩みはなんですか?と、
卒業を控えた彼だからの悩みにみんなが答える一幕も。。
期待の新人「みやぴー」でした(^^)/
やはり、ロボット世代としては、変形メカものが大好きなのです。
はてさて、トランスフォームしたこの物体は。。。というと。
『シーティングバギー』という介護用の車いす。
コンパクトにたためば、乗用車のトランクの収まるほど。
開発者は、おなじみ、北海道立心身障害者総合相談所の西村さん。
シーティングバギーのコンセプトは、楽に座れる事はもちろんのこと、調整のしやすさと、使い勝手。
しかし、いくら優れた道具も、各パーツの意味を理解していないと、かえって使いにくいモノに。。私達も要注意です。
八雲病院に入所しているかたは、主に、外泊用の車いすとして利用しているようですよ。
おさむ講師による、進路学習の授業も最終回を迎えました。
今回のテーマは、「かくしん」
僕らはどこに住み、誰と、何をして過ごすのか?
このテーマを、みんなと考える時間になりました。
・僕らは誰から支援されているか?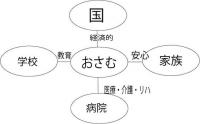
「普段、あまり気にして考えることがありませんが、当然いろいろな支援をうけているわけで、これすべてが、僕らを取り巻く『社会』なんです。学校を卒業するということは、自分を取り巻く社会の図が変わっていくことなんです。」
「『僕らはどこに住み、誰と、何をして過ごすのか』というのを具体的に「なぜそうするのか?」というのを考えないとあいまいになって挫折することになります。そういう所を自分で突き詰めないでいると、人の考えたことだけやって「誰かが行けと言ったから」とか「誰かがやれと言ったから」になって他人のせいで終ってしまいます。結局の所「自分はどうしたのか」の選択は、自己選択し自分自身が決めることです。みんなは学校にいる間は自分の将来について修正・リセットはまだ可能ですが、卒業後に修正するのはかなり難しいものがあります。だからこそ今・この時間にも将来どうしていきたいのか、具体的に自問自答したり、先生と相談したりして一番良い、納得する選択を自分でしてほしいと思いす。時間はわずかです。」
とのこと。
講義の中で、「病院を将来退院したい」といった、生徒に「なぜ?」と質問をしていた場面がありました。
「だって、自由がほしいんだもん。自由はだめ?」
「いや、良いも悪いも、それを決めるのは、自分だから」と。。
私達支援者は、教える側にたってしまうと、
「あなたは、○○にはむいていない・・」
と、人の能力を評価する立場になることがあります。
人が人をさばく(能力を決定する)こととはどういうことなのでしょうか?評価される側は、なにを感じるのでしょうか?
いろいろな場面でこうした、能力評価が行われていますが、いくつその可能性がつみ取られてしまうことになっているのでしょう。
私達ができる支援は、環境の提供くらいなものです。
今回の講義で感じたのは、そうした「おさむくん」の講義を通して、可能性を決してつみとることではない、公正な視点を見たように思います。
あおぞら気分でおなじみの『のぶ』さんが、アシスタント参加する英語授業がありました。本日は、ALTの先生と一緒。ALTのロス先生と『のぶ』さんは、普段よりなじみの中のようです。
みんな、なんでそんなに喋れるの?と思うくらいに、英会話を楽しんでいる!姿に仰天です。(~o~)
のぶさんの英語をきっかけとしたコミュニティーは、いろいろな広がりをみせているようです。次はどんな風景がみられるのか、今から楽しみー(*^_^*)
「みずもしたたる。。。」とかといいますが、それが、汗だとちょっといただけませんよね。(^_^;)
自称「男の汗は勲章だ!」と語る『タムタム」さんは、大のあせかっき。油絵を持つ筆から汗がたらたらと。。
普段、パソコン操作に使っているスイッチも汗で壊れることも。
そこで、タオルのしたにスイッチをおいてみてはとのことで、PPSスイッチを試してみることに。
彼が常用している、ワンキーマウスや、車いす操作のスイッチでは問題なく利用できそうです。
人間の特性に基づいた車いすづくり(2)~実践と研究の統合へ~
の研修会が、北海道大学保健科学研究院でありました。
講師は、北海道大学大学院保健科学研究の井上先生と八田先生、北海道立心身障害者総合相談所の西村重男先生。
生理人類学の視点からのものつくりの話でした。
Orphan(オーファン)という言葉をご存じですか?「みなしご」という意味のようです。海外では、200,000人以下の全体としては0.1%にみたない、小集団への支援が、実はさらに、多くの人々の利益につながる、として、orphan disease(希少疾患)へのorphan productの支援が行われているそうです。
人は多様性をもっていることが特徴ですが、それは、人の数だけデザインがあるというのではない。人の生理的多様性にみられる多型性をみていくことで、「common element(共通要素)」をみつけられないか。このコモンエレメンツこそ、おもしろいとのこと。
また、「Pulse」の事務用イスは、障害者が、人が座ることの、
「common element」を教えてくれたとして、彼らは、「exepert」であると。このようなプロジェクトが、障害を持つかたの能力が劣っている集団という、「ものさし」を変えていくのではと話されていたことが印象的でした。
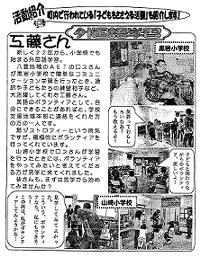
あおぞら気分の『のぶさん』の学校支援ボランティアの様子が、八雲町の子どもサポート便りで紹介されていましたよ。(^-^)
以下は、本文より抜粋。
新しく22年から、小学校でも始まる外国語学習。
八雲地域のA E Tのロスさんが黒岩小学校で簡単なコミュニケーション学習を行ったとき、通訳や子どもたちの練習相手など、大活躍してくれた工藤さん。英語のボランティアとして、自分に.できることがあればと、学校支援地域本部に連絡をくれた方の一人です。
筋ジストロフィーという病気ですが、積極的にボランティアを行ってくれています。山崎小学校でロスさんが学習を行ったときには、ボランティアをやってみたいと考えてくださる方が見学に来てくれました。
皆さんも、まずは見学から始めてみませんか?