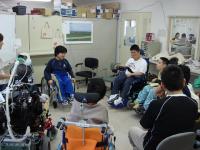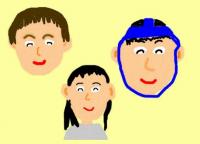「自分の中の引き出しを増やしていく事」
File:03 かなさん
・勉強をする意味とは?
みなさんは勉強は好きでしょうか?「勉強が難しい」とか「勉強がつまらない」などの理由で、ほとんどの人が好きだと答える人はいないと思えます。ですが義務教育が中学校で修了しても、高校・大学・専門学校などと進学をするのが今では当たり前となっています。そんな勉強をする意味とはいったい何なんでしょうか?その理由は好きではない中でも、将来の職に就くためであったり、自分のスキルアップのために進学しているのだと思います。自分の興味のある科目を専攻し、少しでも「知ることは楽しい」と思えれば、勉強を好きになれるのではないのでしょうか?
今回、「コレスペ・ハローワーク」第3回目は、入院生活をしながら日本福祉大学の通信教育部福祉経営学部に通う『かなさん』を紹介します。「勉強」とは何か?その思いを聞きました。
・今、どのような勉強をされていますか?
「福祉に関わるを勉強をしています。今年は、社会福祉学・精神リハビリテーション・社会保障論などの10科目を履修しています。」
・どのような方法で学習をされていますか?
「テキストを読んで勉強しています。わからない所はインターネットなどで調べて、学んでいます。年に4回、科目終了前にテストがあって、それを取れば単位が取得できます。また1度落ちても同じ科目は2回まで受けることができます。」
・以前、放送大学をしていたと聞きましたが、始めたキッカケを教えてください。
「放送大学を始めたのは24・5歳の頃です。高校を卒業してすぐは『もう勉強はしたくない』と思っていました。この頃は自治会の仕事が忙しかったので、自治会の方に力を入れてましたね。ですが自治会の仕事などがない時は、ほとんど時間を持て余すようになっていました。そのうちにもう1度勉強をしたくなったという事と、ちょうど24・5歳の頃ぐらいから周りの友だちが放送大学をやっていたという事があり、福祉や心理の勉強を始めることにしました。」
・放送大学から日本福祉大学へ切り替えた理由を教えてください。
「放送大学を始めてからもずっと『福祉の勉強をしたい』と思って、もっといい学校はないかと探し続けていました。その一つが日本福祉大学でした。日本福祉大学は、『福祉の専門』という事と、試験がインターネットでできるというのを知ったので、日本福祉大学に決めました。30単位くらいを放送大学で取っていたので2年生から編入し、現在は3年生です。」
・勉強をすることでの気持ちの違いや生活の変化はありますか?
「ハリができましたね。それに試験前には勉強したりと、生活にメリハリがつきました。あと気持ち的には『私がんばっている!』という感じがあります。」
・勉強を続けるモチベーションを教えてください。
「せっかくやるからには『卒業したい』というのが一番にありますね。それに卒業とともに資格も取得できるので、それもやる気につながっています。
勉強をすることで、知りたい事や興味のある事を知ることが楽しくて、『もっと知りたい!』と思いますね。」
・勉強をしていて良かったこと何ですか?
「勉強することで、世の中の動きやニュースで話題になってる『自立支援法』や『介護保険』などを、知る機会が増えた事ですかね。」
・日本福祉大学を卒業した後はどのようにしていきたいですか?
「小さい頃から入院をしているのですが、自分と同じように入院をしている方の話を聞いていけるような仕事がしたいと漠然と思っています。ソーシャルワーカーなど。社会福祉士も考えたのですが、実習があるので現実的には、難しいかなと思います。」
・これから日本福祉大学など進学を目指している人へのメッセージをお願いします。
「インターネットで試験ができるので、体の負担は少なくすることできます。自分のペースで勉強することは楽ですが、それではモチベーションを保つのが難しいです。一緒にやっていく仲間とかがいたら、お互いに刺激になっていいのでは?と思いますね。みんなで高め合っていけたらいいですね。」
・編集後記
今回は3回目にして初めて直接インタビューをさせていただきました。やはり緊張してしまい、前の日の夢にまで出てきました(笑)。今まではメールでのインタビューで、そちらの方も緊張したのですが、相手を直接見てインタビューをするので、全然違う雰囲気でした。「徹子の部屋」の黒柳徹子は凄いなーと改めて思いましたね。
僕は勉強の持続性があまりある方ではないので、今回、『かなさん』に「勉強を続けるモチベーション」という事を一番聞きたい質問でした。卒業後の明確な目標や「知ることは楽しい」と思う姿勢が大切なんだということを教わることができました。いつか『かなさん』がソーシャルワーカーなどの仕事に就けるような気がします。またその時はインタビューをさせていただければ、嬉しいです。。
(おさむ)