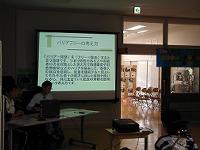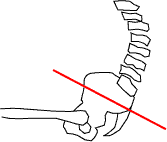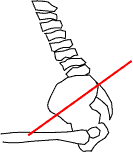去る2006年2月7日(水)札幌市教育文化会館大ホールにて、北海道保健福祉部福祉局障害者保健福祉課主催による「障がい者の就労支援に向けた道民フォーラム」が開催されました。当事者、福祉関係者、教育関係者、労働関係者、一般企業から約700人が集まり、「障がいがあっても働ける」「障がい者とともに働く地域社会づくり」について考えました。
障害者雇用促進法では、一定規模の企業での障害者雇用が義務づけられていますが、なかなか雇用が進まない現状があります。雇用問題では、多くの問題が指摘されていますが、もしかすると、「なんだか、障害を持つ方とどう接してよいかわかならない。」そんなことから溝が始まっているのかもしれません。
障害者を積極的に雇用している(株)アイワード社長さんが「はじめは一人の採用から始まった」「障がい者を雇用したことにより、従業員全体に安全性に対する意識やコミュニケーションが生まれ、企業価値が高まった」と話されていました。
”産むがやすし”
日本では障害を持つ方は優しく見守ることの意識があり、障害者が働くなんて!!と、どこか、私たちの世界と違うように隔てている空気があるような気がします。障害があっても働ける社会づくりをコレスペも応援します。
(元木特派員)